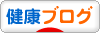〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷1丁目24−8
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
| 15:00~17.00 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
休診日:月曜、木曜、金曜、日曜、祝日
午後休診:土曜 @メールからの完全予約制です@
肩こり外来の記事と重複するのですが、肩こりに対しての私の考え方、患者様への治療法などをひとつにまとめようと考えて文章を書き連ねてみました。
少し古い内容ですが参考にしてください。
肩こりは有病率でみればおそらく男女ともに日本で一番多い病気ではないかと思います。
その「肩こり」を説明する、または定義してみましょう。
整形外科の専門医の集まりである日本整形外科学会のなかでは肩こりの定義を肩、頚、肩甲帯部の「固くなった感じ」「張っている感じ」「重苦しい感じ」「痛い感じ」としています。
つまり病名というよりは「自覚する症状」ととらえているのです。
マッサージにかかったとき「ずいぶん肩がこっていますね」といわれた経験は無いでしょうか?
この場合の{凝り}はマッサージの先生が患者さんのからだに直接手を触れて感じ取れる筋肉の緊張のことだと思います。
不思議なことに筋肉自体が硬く凝っていても「肩がこった感覚」を自覚していない人も大勢います。
逆にあまり筋肉が硬くこってなくても「肩がこってつらい、頭痛や吐き気までする」と悩んでいる人もいます。
肩こりはあくまで自覚症状であり「病名」ではないわけです。
日本人は体の部位をさす言葉の中で結構「かた」を意識して使っています。
「肩がこる」以外でも「肩身が狭い」「肩の荷を降ろす」「肩たたきにあった」などの言葉もありますね。
これに対し欧米では体の部位をさす言葉として「かた」をさす単語をあまり意識して
使っていないという話を聞いたことがあります。
時々「外国人には肩こりが無いそうですがほんとうですか?」と質問を受けます。これは
おそらく「肩」を意識して使ってないため「肩こり」に相当する言葉が見つけにくいのではないでしょうか。「肩こり」を「背中の痛み」「首の痛み」と表現しているのではないかと想像しますがいかがでしょう?
肩こりという症状を起こす病気は整形外科の疾患以外にも精神科、歯科口腔外科、耳鼻咽喉科、眼科、脳神経外科、婦人科、内科など多くの臨床科のなかでおこってきます。
しかし多くの患者様の肩こりはほかに病気があって起こってくるものではなく、明らかな病気がはっきりしないことが多いと思います。
このような原因のはっきりしない肩こりを本態性の肩こり、病気があって起こってくる肩こりを二次性かたこりと仮に分類し話してゆきます。
本態性の肩こり
それでは本態性の肩こりにはなにも原因がないのでしょうか?
診察をしても原因につながる手がかりがないわけですが、症状がある限り症状をひきおこす原因はどこかに隠れていると考えたほうが良いと思います。
背景に過労、運動不足、不眠、冷え、姿勢異常などがある場合が多いといわれていますが
このことを意識して診察してくれる先生が少ないのが現状です。
肩こりに積極的に取り組んでなければなかなか原因にまでたどり着くことは難しいかもしれません。
肩こりの患者様の多くは医療機関にかかっても特に異常を指摘されず、湿布などで対処してもらっているのです。これではなかなか「肩こり」は治ってはくれません。
私のクリニックを受診した肩こりの患者様を見る限り
姿勢の異常(または姿勢異常を起こす病気)が肩こりに影響している人がかなり多く認められます。
それに肩こりに加えて頭痛もちの方が多いのも特徴です。
首から肩にかけての筋肉に異常な緊張がつづいて、不快なこり感、肩の重さ、痛みなどが起こることは多くの人が経験されていると思います。
いろいろな形で首から肩にかけての筋肉に緊張が起こるのですが、その誘引、原因を少し話してみたいと思います。
1)肩に負担のかかるような無理な姿勢
肩こりにかかわる筋肉にいつも同じような負担がかかっていると、筋肉の血流が悪くなり肩がこってきます。
たとえば、長い時間机に向かって仕事をする。
腹臥位(腹ばい)で本を読む。
横に寝てテレビをみる。
など、無理な姿勢が長く続くと肩がこることになります。
筋肉は緊張したり、弛緩したりを繰り返すことで血液が流れるようになっています。
いつも同じ姿勢で同じ筋肉が緊張し続けると筋肉の血流が悪くなり疲労物質もたまってしまいます。
思い当たることがあるようでしたら、同じ姿勢を長く取らないように工夫をしてみてください。一時間に一度でも肩残りをほぐすような体操をしてみるのも良いかと思います。
体に無理な姿勢が肩の凝りの原因になることと、その解消に運動をすることが大切だとおはなししましたが、
■「円背」という言葉をご存知でしょうか?
ご高齢の方で背中が丸く曲がってしまった状態です。
姿勢が悪いわけですが、背中が丸く曲がったためいつでも下を見るようになってしまいます。普通に前を見ようと思うと首を持ち上げなければなりません。
皆さんも、首を伸展させて空を見続けてみてください。ずっとこの状態を続けると首の後が苦しくなります。
円背の方は普通に前を見ようとするときこのつらい姿勢をとることになり、首肩の筋肉の緊張を強いられます。
このような人は軽く運動をした程度では首の凝り感が取れないことが多いようです。
最近はこの「姿勢異常」が原因で肩がこっていると思う患者様が増えているように思います。しかしその「姿勢異常」は円背ではなく「側弯」が多いのです。
「側弯」についてはこの後の整形外科の疾患のところでお話をします。
2)視力調整、眼精疲労
次に、肩こりの原因のひとつに視力調整がうまくできてないときがあります。
めがねやコンタクトレンズがあわないために目が疲れたり、細かい作業を集中してすることにより起こります。
最近はコンピュータ端末を長時間操作する方が多く、このような方に肩こりが多くみられます。
対処法はやはり眼精疲労を改善することになるかと思います。
無理な姿勢を長い時間取ったりするのも体へのストレスですが、眼精疲労もやはり体へのストレスということになります。
めがねが合ってないならやはり眼科にかかってみることです。調整していただくことで慢性的な肩こりや眼の奥の痛みがあっさりなくなってしまうことも多々あります。
肩こりがあって整形外科を受診した場合、整形外科の先生はまず姿勢異常がないかを観察します。さらに首から出る神経の異常がないか診察し、頚椎のレントゲン撮影をして首の骨に異常がないかを見ます。姿勢異常については以前にお話していますのでそちらを見てください。
老化による首の骨の変形があると肩がこる場合があります。首の骨から出た神経が肩から上肢の運動と知覚をつかさどっていますのでここに問題があると首の痛み、手のしびれなどがおきる事があり、中には肩こりだけが起こっている人も見受けられます。
今週になり肩こりがあって受診した患者様は3人おいでですがこのうち一人のかたに頚椎の異常を認めています。ただ、頚椎に異常があって肩がこる人は肩こり全体から見れば少数派です。
3)筋力低下
肩こりの原因として筋力の衰えがその原因になっていることもあります。
肥満や、極度の痩せ体型の人が運動不足をおこして肩の筋肉の衰えをおこしてくることがあります。
筋力の衰えがある人が肩にストレスのかかる運動負荷をうけるとすぐに肩の筋肉に疲労物質がたまり、肩凝り感を自覚することになるのです。高齢者もそうです。
このように考えてくると、老化で姿勢が悪くなり、首の骨にも老化による異常があってさらに首、肩の筋力が衰えているような方は常に肩がこることになってきますね。
また多発性筋炎のような病気で頚部の筋力が低下すると首が自然と前に傾いてしまう
「くびたれ」現象がおきます。
いつも下を向いていなければならず肩のこり感も頑固なものです。
4)寒冷
寒さが肩のこりに関係してくることもあります。
寒さにより肩周囲の筋肉が緊張することと、血管がちぢこまることで筋肉内の血流が悪くなります。こうなると肩がこってきます。
夏場でもエアコンを効かしすぎて肩を冷やす可能性もあり、油断ができません。
オフィスでのデスクワークをされている方は、この冷えと座り続けることによる姿勢性のストレスとさらに眼精疲労、気のあわない職場の上司からのストレスと、肩凝りの原因には事欠きません。
体の冷えは肩凝りだけでなくいろいろな症状を起こしてきます。
頭痛や腰痛も体の冷えを原因に起こる事があります。
現代人はいろいろなストレスをかかえて体力がないためかもしれませんがからだを燃やすエネルギーが乏しく「冷え症」の人が多いと思います。
この体の冷えについては機会をあらため話してゆきたいと思います。
5)精神的ストレス
慢性的な肩こりを訴えて「肩こり外来」を受診する患者様の中に抗うつ剤や向精神薬を服用している方が少なからず存在します。
うつ病などの心の病気では頭重感や肩こりを多くの方が訴えます。
私たちの体に不調が起きたとき、その症状を引き起こす病気は一つとは限りません。
腰痛の原因になる病気をとってみても、椎間板ヘルニア、腰部脊椎管狭窄症などを代表として多くの病気の可能性が考えられます。
整形外科の外来では患者様の訴える症状と体を診察させていただき、精密検査などから痛みの原因を探って行きます。
肩こりも同じような手順で診察してゆきます。
★ 二次性のかたこり
肩こりという症状を引き起こす病気にはどのようなものがあるのか
いくつか病名を列挙してみます。
■内科疾患
高血圧症
血圧が高いと項頚部のこり感が生じるといわれています。私の狭い経験の中では血圧が高くて肩こりがある人はあまり経験がありません。高血圧の人で急に血圧が一段とたかくなった時に肩、頚のこり感を訴えた方が何人かいるだけです。
貧血症
貧血になると血液の酸素を運ぶ力が低下します。筋肉を使い続けるためには血液からの酸素の供給が必要です。貧血によりその酸素を運ぶ能力が低下すると酸素不足から筋肉はすぐに疲弊してしまいます。貧血症の方はパソコン入力などデスクワークでも肩頚の筋肉を使う時に常に一定の姿勢をとり続けるだけでも筋肉は酸素不足に陥り悲鳴を上げます。
胃炎、胃潰瘍
胆石症、胆嚢炎
関連痛として肩甲帯の張り感、こり感を自覚される方がいます。右肩がこることが多いそうです
膵炎、胃炎、胃潰瘍
関連痛として肩甲帯の張り感、こり感を自覚される方がいます。左肩がこることが多いそうです。
狭心症、心筋梗塞などの冠疾患
左肩甲部への放散痛が肩こりと間違われることもあります
胸膜炎・肺ガン
肺の一番上部にガンができると肩こりをはじめいろいろな症状が起きてきます。
自律神経失調による多彩な症状が起こることもあります。
■耳鼻科疾患
メニエール病
この病気の50%で肩こりを自覚するとの報告があります。
■婦人科疾患
更年期障害:この時期は多彩なからだの不調が起こりますがその中に「がんこな肩こり」も入ってきます。
子宮筋腫や子宮内膜症も肩こりを起こします。子宮筋腫は貧血をひきおこしますので肩が凝ってもおかしくは無いですね。
東洋医学的には「おけつ」のある人には肩こりが起こる可能性があります。
■精神科疾患
うつ病、心身症では肩こりを訴える場合が多いそうです。
■歯科口腔外科
咬合の異常
歯の治療で詰め物やブリッジを作ったあと、微妙なかみ合わせの変化が生じます。これをきっかけに肩こりが出てくる方もいます。
顎関節症
顎関節の痛みが肩、肩甲部の筋肉の緊張をひきおこして「肩こり」を生じるようになります。当然咬み合わせにも影響します。
■ 神経内科・脳外科
頚部ジストニア(痙性斜径)
首の筋肉が自分の意思と関係なく緊張してしまう病気です。気がつくと頭が左右へ傾いていたり回旋していたりします。首が前にたれてしまう「首たれ」もこの病気のことがあります。原因がまだはっきりと特定されていません。
神経的ストレス、運動、歩行などで増悪し、安静、臥床、睡眠により消失するのが特徴です。30〜40歳代に多発し、社会生活に支障をきたすこともあります。
姿勢の悪さから頑固な肩こりをひきおこします。
ジストニアは全身性のものから局所性のものまであります。
「書痙」もジストニアのひとつです。文字を書こうとすると筆先がふるえ思うように文字がかけない状態です。
ゴルフのときにも同じような状態が起こります。イップスというそうです。
パターでボールを打とうとするとき、思わぬ力が入って何メートルもボールを転がしてしまう人がいます。このような人の中にもジストニアという病気の場合があります。
治療にはボツリヌス菌の毒素を弱毒化させて薬として使えるようにしたものが現在注射薬として存在します。頚部の筋肉に注射してあげると症状の改善につながります。
最近コブクロのメンバーがかかった病気も、声を出そうとしたときに自分の意思と関係なく首の筋肉が緊張して声が出せなくなる状態になる発声時頸部ジストニア(痙性発声障害)といわれていますね。
この病気の人は通常、体のどこかに本態性振戦が起こるといわれているそうです。
この方にも肩こりがあるのか興味深いですね。
★おなじように首や頭が傾いてしまう状態をひきおこすものに側弯症があります。
私のクリニックに肩こりで受診される患者様では、頚部ジストニアの患者様よりは側弯症の患者様のほうが圧倒的に多く受診されます。
■ 整形外科領域の病気
まずは頚椎に関わる疾患があげられます。
頚肩腕症候群という言葉があります。
1955年に飯野三郎先生、河邨文一朗先生により提唱された名称です。
頚から肩、腕のこりや痛み・疲労感、脱力感、手指のしびれや冷感を来す疾患を総称して頚肩腕症候群と呼びます。
私は「肩こり」を訴えて受診した患者様にはとりあえずこの頚肩腕症候群という病名をつけて診察を進めてゆきます。病気がみつかればその時点で訂正します。
1)変形性脊椎症
レントゲンで診断できる頚椎、胸椎、腰椎の老化による変形を主体とした病名です。
頚部の変形がある方は胸椎も変形していることも多いようです。
円背といって背中が丸くなり前かがみの姿勢が強くなると、首を無理にあげるためにいつも肩・首の筋肉が緊張してしまいます。その結果肩がこることになります。姿勢異常による肩こりのひとつです。
また頚椎を固定している椎間関節も老化して変形します。普段はなんでもないのですが、時に椎間関節の動きが悪く首の動きにつれ痛みが出ることがあります。このような時も「肩こり」を訴える方がいます。
2)胸郭出口症候群
頚椎のたかさで脊髄神経の枝が首の骨の隙間を通って外に出て、首の筋肉の間を走り腕や肩甲部、背中の運動と知覚をつかさどっています。
この神経に影響が出て肩こり、腕のだるさ、手のしびれなどを起こす病気です。
最近この病気の患者様が増えています。
★ 胸郭出口症候群チェックリスト
首こり、肩こりがあり、下の項目に2個以上チェックが入れば
胸郭出口症候群の可能性があります
一度整形外科を受診しましょう
両腕で抱えて持てばまだらくだが、ものを下げて持つと肩がつらくなる
ソファーの背もたれに腕を挙げて置けば肩は楽
つり革 に長くつかまれない 腕や肩が痛くなる
肩にバッグかけるとつらい
腕や手がだるい、しびれる、いたい
首の付け根がいつも張っている、凝っている感じがする
首の付け根を押すと痛い、
3)いわゆる四十肩、五十肩
患者様の訴えが「肩がこる痛い、腕が重く違和感がある」という場合ただの肩こりではなく四十肩、五十肩のことがあります。肩関節周囲の痛みが腕や肩、首へ影響を及ぼしていることがあるためです。
4)側弯症
脊椎は前後方向から見たときはまっすぐに配列されています
これが正面から見て 弯曲した状態を側弯症といいます。
脊椎の胸の部分に側弯があるとその影響で左右どちらかの肩が傾いたり、首が左右どちらかに傾いている人がいます。この姿勢の悪さがあるといつも肩、首の筋肉の緊張を強いられることになります。筋肉がくたびれてくると痛みやコリが起こってしまいます。
小学生、中学生のころから肩こりがあるという人に多い肩こりの原因のひとつです。
★頭痛と肩こり
よく肩こりがひどくなると頭痛がすると訴える患者様がいます。
肩がこると頚部から肩甲部、背部の筋肉が硬く緊張してきます。
この筋肉は後頭部に付着していますから肩のこりが悪化すると後頭部の痛みがでてくることがあります。
頭痛の分類の中で緊張型の頭痛と分類される頭痛の一部がこれに当たります。
頭痛の中でも緊張型頭痛はかなり多く存在します。
この型の頭痛はいつもだらだらと頭痛が存在します。
でも緊張型の頭痛が原因ですべて肩こりが起こるわけではありません。
患者様の中には肩こりに頭痛が併発するとその頭痛は緊張型頭痛だと思っている人もいますがそうではありません。
偏頭痛も肩こりを伴うことがあります。偏頭痛の患者さんは普段は何も痛くないのですが
何かをきっかけに頭痛発作が始まります。
偏頭痛の患者様のなかには頭痛がきそうな時に何となく発作がきそうなことをわかっている方がいます。突然目の前にきらきらと光が見える現象です。
これが起こると暫くして頭痛が始まります。典型的な偏頭痛の患者様に認められるものです。閃輝暗点といいます。
芥川竜之介の小説の中にこの閃輝暗点の記載があります。
遺稿となった「歯車」という小説です。このなかに詳細な閃輝暗点の記述があります。
芥川自身はこの現象が発狂する前触れではないかと悩んでいたようです。
この短編を中学校の国語に授業で読まされた記憶があります。
当時は片頭痛の知識も無く、国語の教師も特に片頭痛についてまでは解説はしていただけなかったと思います。
この前兆を持つ偏頭痛は偏頭痛患者さんの20%前後と考えられています。
あとの偏頭痛患者さんには前兆がないといっても、偏頭痛の患者様では何となく頭痛がくることを予測できること(予兆)があります。
★たとえば肩こりがすると頭痛がするという場合がそれにあたります。★
そしてこの肩こりと頭痛の関係は比較的見逃されていることが多く見受けられます。
私のクリニックの「肩こり外来」を受診する患者様の1割前後の患者様に頭痛が関与しているのではと疑わせる方がいます。
肩こり以外のあくびなどの片頭痛の予兆は発作がおさまれば消えてしまいます。
しかし肩こりから起こる偏頭痛の場合、頭痛発作が改善した後も暫く肩こりは続くことが多いようです。
肩こりの治療に先行して頭痛の治療(予防)をしてゆくと、
頭痛治療だけでご本人の訴える「肩こり」が軽くなってしまうケースが多々あります。
極端な例では頭痛を予防することで「肩こり」はそれ以上の治療をしなくてもすんでしまうのです
偏頭痛の治療薬は頭痛発作が起き始める時期にタイミングよく飲むとその治療効果がおおきくなります。したがって肩こりを予兆とする偏頭痛の患者様は頭痛治療のタイミングをうまく推し量れることが多いようです。
肩こりを放置しておくとどうなるでしょう?
多くの方はつらい肩こりがそれ以上変化することは少ないのですが、中には頭痛、眼がしょぼつく、嘔気、手や腕のだるさ、しびれ、不眠などほかの症状が加わってしまうひとがいます。
★どのようなときに病院にかかればよいでしょうか?
肩こりが悪化して日常生活に差しさわりがある場合
頭痛、眼がしょぼつく、嘔気、手や腕のだるさ、しびれ、不眠など多彩な症状を呈するとき
マッサージなどで一時的に良くなっても繰り返し肩がこる場合
普段からの肩こりが悪化したとき
★ 治療のあらまし
肩こりの治療は一種類の治療法で簡単に治ることはあまりありません。
その方の体の状態にあった治療法をいくつか選び組み合わせて治療することが大切です
。
整形外科などの医療機関にかかった場合の肩こり治療はどのようなものがあるか考えて見ましょう。
診察した結果とくに異常がない肩こりの場合はまず物理療法をしてみます。
こった肩の筋肉をほぐす目的で、肩周囲に温熱療法をすることがあります。
私のクリニックでは機械を使い<マイクロウェーブ>を肩に照射して暖めたりします。さらにマイクロウェルダーという機械で肩を振動させ、温めながら磁気治療をしたりします。またあとで出てきますが星状神経節ブロックという方法の代替療法として近赤外線を頚部に照射する<アルファ−ビーム>という器械もあります。ブロック注射をしないでブロック注射の効果を得ることを目的におこないます。
首への注射に抵抗感のある人には良いのではないでしょうか。
次に牽引療法があります。
頚部を引っ張ることで肩こりが楽になることは経験的にわかっています。大変有効な方法ですが、その作用機序はまだあまり解明されてはいません。牽引する力が
当院の機械ですと首を牽引しながら暖められる機能があり上記の温熱療法を兼ねることができ有用です。
次に干渉波治療器、低周波治療器も肩こりに有効です。
皆さんのお家にも家庭用の低周波治療器があるかもしれません。
クリニックにある器械は家庭用よりも出力、刺激パターンなどを強化してあり効果的です。
こった筋肉にリズミカルな刺激をくわえることでこりを取ります。経験してみればわかりますが気持ちよい治療ですよ。
■肩こりをお薬で治してゆくことを考えてみましょう。
筋弛緩剤
肩こりのある人は肩周囲の筋肉が異常に緊張しており、肩の血流も悪くなっています。このため筋肉内に疲労物質がたまりコリ感、痛みが増強しています。
この異常な筋肉の緊張をやわらげられれば肩のコリ感も軽くなると考えられます。
そのために用いられるお薬として「筋弛緩剤」というものがあります。
筋弛緩剤は手術で全身麻酔をかけるときに完全に呼吸を止め、呼吸をコントロールすることや、おなかの筋肉を完全に弛緩させ手術とやりやすくする目的で使われもします。
肩こりの時には完全な筋弛緩までは必要ではありませんが、マイルドな効き具合の飲み薬が用意されています。
鎮痛消炎剤
筋弛緩剤だけでも効果が出ない人には、鎮痛消炎剤をあわせて服用していただきます。肩周囲の筋肉内の血流が悪いとその場所に痛みを発現する物質が出てきます。
この痛みに対してはいわゆる「痛み止め」が有効です。
漢方薬
鎮痛消炎剤は胃炎や胃潰瘍などの胃腸障害が副作用として起こる可能性が高いくすりです。
生まれつき胃腸の弱い方には鎮痛消炎剤が使えないこともあります。
このようなときに漢方薬が役に立ちます。
肩のこりだけでなく整形外科にかかわる多くの病気にも漢方薬は応用が効きます。
患者様一人一人の体質を見極めたうえで漢方薬を使えばかなりの効き目を発現します。
肩がこっている患者様も東洋医学の診察方法で眺めてみるといろいろな「偏り」を発見できる場合が多々あります。その「偏り」を補正してゆく事で「肩こり」も解消できることが多いものです。
■ 注射
トリガーポイント注射
注射で凝った筋肉に局所麻酔剤を注入してあげると筋肉内の血管が拡張し血流がよくなります。血流がよくなると凝った筋肉内の疲労物質、痛みの発現物質が洗い流されて肩のこりが軽くなります。高齢者の方から若い方まで幅広くおこなうことができ、比較的副作用も少ないものです。
神経ブロック注射
肩の凝りに有効な神経ブロック注射には肩甲上神経ブロックや、星状神経節ブロックがあります。頑固な肩の凝りに一度試してみると良いと思います。
注射が苦手な方には星状神経節ブロックの代わりにアルファ−ビームという器械を用いることもできます。星状神経節ブロックの注射部位にこの器械から赤外線を照射しますとブロックをしたときと同じ効果が得られます。
胎盤エキス注射
プラセンタ注射ともいいます
プラセンタ注射は1950年代から肝障害、乳汁分泌不全症、更年期障害などに使われ続けているお薬です。
プラセンタ注射が開発される前には「胎盤埋没療法」という治療法がありました。
「胎盤埋没療法」は1930年代にソビエトのフィラートフ博士が開発したものです。
冷蔵保存し処理をした胎盤の切片を人の皮膚の下に埋め込むことで病気をなおそうという治療法です。
プラセンタ注射はこの「胎盤埋没療法」をより安全に、簡単に行えるように開発されてきたものです。
これまでに大変多くの方に使われてきましたが副作用の報告もごく少なく、使われる過程で肝障害、乳汁分泌不全症、更年期障害以外の病気を改善してくれることがわかってきました。しかし、プラセンタ注射が効果を発揮するメカニズムはまだ解明されてないのが現状です。
生理不順、月経痛など女性特有の病気にも効果があります。肌の老化、しわ、しみなどにも有効だといわれています。整形外科の病気では関節リウマチ、腰部脊椎管狭窄症などでも治療効果が期待できます。
このプラセンタ注射が肩こりの改善に効果的なこともわかってきました。私のクリニックでは「肩こり外来」を開いていますが、通院する患者様でなかなか肩こりの改善がない方にご提案させていただいているお薬です。
中には一回の注射で長年悩んでいた肩こりが改善した人もいます
全てのケースに有効とまではいえませんがいろいろな治療をしてもなかなか改善しない患者様には一度体験していただきたい治療法です。
ボトックス注射
現在当院では行っていません。
★自分でできる肩こりの予防についてかんがえて見ましょう
①適度な運動
筋肉を使うことが肩こりの予防になる
使うことで筋肉内の血流が良くなる
使いことで筋力の低下が防げる
体幹の筋肉が鍛えられると姿勢が良くなることになる
ストレッチ体操はしたほうが良い
痛く気持ちよいところまでストレッチする人が多いが効果が薄い
②姿勢を良くすること、無理な姿勢をとらないこと
猫背は良くない
無理な姿勢は頸、肩ノ筋肉に負担がかかる
③デスクワークには肩こりになりやすい要素が多い
PC:眼精疲労、入力に手先を使い、腕を浮かせていると肩の筋肉に疲労が出やすい
同一姿勢を長くとる
単純作業でストレスがたまりやすい
いすや机は自分の体格にあったものを選ぶこと
いすの高さ、背もたれの高さ、角度 浅く座らない
机の高さも注意を
④肥満
腹が出ると反っくり返った姿勢をとることになる
運動が不足しがちで筋肉に疲労物質がたまりやすい
肥満の人が冷え症になるとやっかいです。
⑤肩を冷やさない工夫を
冷えれば筋肉はかたくなり、筋肉内の血行が悪くなり疲労物質、発痛物質がたまりやすい。
エアコン
上着を羽織る、ひざ掛けを使う、体全体を冷やさない
からだを冷やす冷たい飲み物や食べ物は避けましょう
★逆に暖めると肩こりの解消につながります
家庭でも肩、首をあたためるようにしましょう。たとえばお風呂でシャワーを使い肩、首を暖めるとよいとおもいます。また髪を乾かすドライヤーの熱風を使うのも方法です。
冬場にでまわる使い捨てのカイロも結構効きます。(低温やけどには十分気をつけて使ってください)
⑥同じ作業を長い時間繰り返さない
特に上肢をつかい肩の同じ筋肉に負荷がかかると良くない
腕を浮かせて作業をしないように
⑦肩のマッサージ
肩を揉んでもらうのは良いが、もみかたが強すぎると良くない。逆に筋肉が硬くなりこり感だけでなく、痛みも出てくる
同じことだが肩をたたいてもらうのも強さを加減すること
強くたたきすぎたり揉み過ぎたりすると微小血管を破綻させ小さな出血を起こし、疼痛の増大につながる
⑧充分に睡眠をとる
充分に睡眠をとることで疲労を体に溜め込まないようにしてください。
睡眠時の枕の高さも最近は大切だといわれています。
自分に合った枕を選んでみる事も肩こりの予防には良いことだとおもいます。
⑨からだにあわない服装・・キチキチの腹は着ない
⑩ストレスをためない
★ 「肩こり外来」受診を勧める肩の凝り
かなり昔、十代のころから肩がこる
肩がこると頭痛がする、吐き気がする、腕が痛い、顎関節が痛いなど他の症状が出るとき
肩こりに加え腕や手ががだるい、しびれる、いたい
普段よりも肩こりの程度が悪化しつらいとき
マッサージや鍼灸をすれば一時的には良くなるがすぐにまたかたがこる
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
| 15:00~18:00 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
漢方薬治療
慢性症状・不定愁訴コンサルタント 平沼 尚和
漢方、整形外科、麻酔科の経験から治療を行います
お気軽にお問合せください

ネットで予約してください
電話では予約できません
<診療時間>
午前 10:00~12:00
午後 15:00~17:00
※火曜、水曜 午前午後
土曜は午前中のみ